つくたま塾 2014年6月25日 19時~21時の記録
◎講師:水口俊典氏(芝浦工業大学名誉教授/一般財団法人都市農地活用支援センター理事)
◎参加者:18名
◎タイトル:「市街地の中の農地の行方と都市農地保全のまちづくり」
[概要]
我が国の都市は諸線引きが1970年以降になされ、大都市圏などで市街化区域と市街化調整区域に区分されている。市街化区域は都市基盤が整備される区域であるが、大量の農地が初めから含まれてしまった。その扱い方に関する都市計画上の理念と、農地を宅地化するか保全するかの実践に関わる変遷が、講義内容である。そうした都市農地を扱う法制度は計画規制、税金(相続税など)、大都市圏域、都市計画事業制度、農地の利用に関する制度などが複雑に絡み合っている。水口氏は自らの菜園づくりの実践とからみ合わせながら、都市住民の問題としてもこのテーマを取り上げた。
・講義はテキストⅠに沿ってなされたので、参照されたい。以下のまとめは当日のお話からピックアップした要点の一部である。
1 都市農地のあり方議論の時代的な転換
当初線引きの大きな目標は、農地の宅地化促進であった。しかし、大量に農地があり、一方、保有意欲の高く農業生産に意欲的な農地所有者等への対応するために、農地の存在を認めるか否かの議論と制度化がなされ、1991年に生産緑地制度が改正され、農地存続が認められたことで一応の区切りが付いた。
その頃から、「都市化圧力の減殺、市民の食の安全性への関心、都市気象異変への対応など」様々な事情から農地保全への機運が高まった。しかし、農地を保有する第2種兼業農家そのものが実態を希薄化していく現状も強まっている。
だが、都市内の農地を認める都市計画制度のあり方については様々な議論がされ、ようやく近年になり国の政策において総論的に認められてきた。しかし、10年ごとに見直される農住組合法は、農地を活かした多様なまちづくりを実質的に進めてきたのだが、2011年に事実上の廃止が決まった。講師はこの制度の特徴的な実践に期待していたのであるが、廃止を大変残念と思っている。国レベルでは具体的な各種の法制度の見直しにつながらないまま、現在にいたっている。
2 市民農園の体験的問題点として、公営市民農園はモデル的な意味はあるが、継続的な農作業がしにくく、農園環境もクラインガルテンなどと比べて雲泥の差がある。私営市民農園は、自作農の存在を農地法制度に位置付けたDNA的な問題が潜んでいて、農地の貸し借りの安定性が欠ける。講師は現在、私営市民農園でほぼ150%の野菜の自給率を誇っており、その楽しみを味わっている。
3 地域特性に応じた農地保全手法が展開されることが今後の方向性だろう。3大都市圏の特定市には10,000haを超える生産緑地があり、2022年に建築制限が解除される。それらを含む都市農地をいかに保全し、良好な都市環境を創造していくかが大きなテーマになるだろう。補償付き農住地区計画制度や田園風致地区制度などの注目すべき提案もあり、農地相続税納税猶予制度と都市計画との再結合なども考えられる。世田谷区の「農地保全重点地区」は自治体レベルの取り組みとして注目される。
◎質疑を含めた意見交換では、JAの役割について、埼玉県内W市の実情、都内I区における都市農業方針策定後のその後の展開についてなど、このテーマの多様性が改めて認識された。
配布資料
○テキストⅠ:「都市農地保全のまちづくり―市民農園体験を交えて―」『土地総合研究』2013年夏号
○テキストⅡ:「生産緑地の変遷と市街地の中の農地の行方」『新都市』64巻10号2010年、抜粋 都市計画協会『都市計画法制90周年記念特別企画集』2011年所収
○参考図表等:参1~参8、農水省、国交省の審議会参考資料等から、都市農地の現況、制度概要、国の検討状況等を示したもの
○都市農地センターのパンフ:「『農』のある暮らしづくりアドバイザー派遣事業」
話の順
●テキストⅠ:1.都市農地のあり方議論の時代的な転換
○テキストⅡp.1-2:当初線引きから新生産緑地までの変遷
○参1、2:市民農園の推移、市街化区域内農地の推移、生産緑地の買取り申出
○参8:社会資本整備審議会都市計画制度小委員会中間まとめ1209抜粋
●テキストⅠ:2.市民農園の体験的問題点
●テキストⅠ:3.地域特性に対応した都市農地の保全手法
○参3:農住地区計画概念図
○参4:市街化区域内農地を都市公園として保全する例
○参5、6、7:農地継続の支障要因、農地における行為制限と課税の関係、相続税の納税猶予の特例
●テキストⅡp.3-7 資料:生産緑地等を保全活用したまちづくり事例
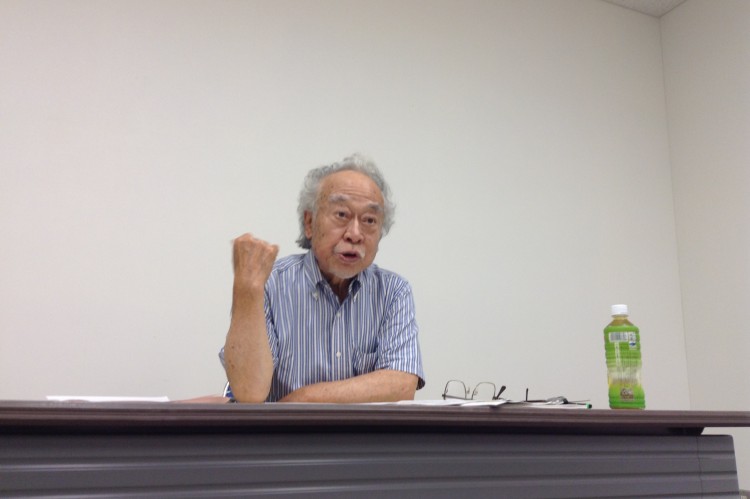

水口理事の常々おっしゃっている内容です。都市農業振興基本法が新たに制定され、都市農業が保全される方向に進んでおります。
以下に、(一財)都市農地活用支援センターが取り組んでいる事業を紹介します。
「農」のある暮らしづくりアドバイザー派遣事業は、農水省の交付金を受けて実施しています。専門の知識を持ったアドバイザーを無料で派遣致します。
詳しくは、
https://www.tosinouti.or.jp/
をご覧ください。